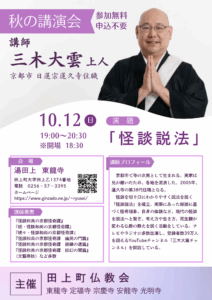お盆の意義と、いのちの繋がり
まもなく私たちはお盆の時期を迎えます。お盆と申しますと、ご先祖様をお迎えし、ご供養を捧げる大切な期間でございます。皆様それぞれの心に、亡き方々への想いが深く去来していることと存じます。
このお盆というご縁に際し、改めて「いのちの繋がり」について、お釈迦様、道元禅師、瑩山禅師といったお祖師様のお示しくださった道を辿りながら、ご一緒に考えてみたいと思います。

お釈迦様が説かれた「縁起」の教え
まず、お釈迦様は私たちが生きるこの世のありようを、「縁起(えんぎ)」という言葉でお示しくださいました。縁起とは、すべてのものが独立して存在しているのではなく、様々な「縁」によって生じ、支え合っているという真理でございます。
私たち一人ひとりの「いのち」もまた、決して単独で存在しているのではありません。父がいて、母がいて、そのまた父、そのまた母と、遠い祖先から連綿と続く「いのちのバトン」を受け継いで、今ここに生かされています。そして、衣食住の全てにおいて、多くの人々の営みや自然の恵みに支えられて、私たちは日々を暮らしております。
この縁起の教えに照らしてみれば、ご先祖様との繋がりは、まさに私たちのいのちの根源であります。ご先祖様なくして、今の私達は存在し得ない。この当たり前の事実の中にこそ、感謝すべき尊い縁があることを、お釈迦様はお示しくださったのでございます。
道元禅師の「只管打坐」と「修証一等」
さて、私たち曹洞宗の大本山永平寺をお開きになった道元禅師は、この「いのちの繋がり」を深く見つめる実践として、「只管打坐(しかんたざ)」、ひたすらに坐ることをお勧めになられました。
只管打坐は、何か特別な悟りを求めるのではなく、ただひたすらに坐禅をする中で、私たちが本来持っている仏様の心、清らかな心に立ち返る実践でございます。坐禅中に、ご先祖様や故人の面影が心に浮かぶこともあるでしょう。その時、ご先祖様が私達に与えてくださった「いのち」というかけがえのない贈り物を、ただ静かに受け止める時間が、私たちをより深く、ご先祖様との縁に結びつけてくれるのではないでしょうか。
また、道元禅師は「修証一等(しゅしょういっとう)」という言葉もお示しになられました。修行と悟りは別々のものではなく、修行そのものが悟りである、という教えであります。ご先祖様へのご供養もまた、単なる形式ではなく、ご先祖様の恩に報いるという「修行」そのものが、私たち自身の心を清め、安らぎへと導く「悟り」の道に通じていると拝察いたします。
瑩山禅師の「利他」と「報恩」
そして、太祖でいらっしゃいます大本山總持寺をお開きになった瑩山禅師は、道元禅師の教えを受け継ぎ、さらに多くの人々が仏道に親しめるよう、布教に尽力なさいました。瑩山禅師の教えの根底には、「利他(りた)」、すなわち他者を慈しみ、助ける心がございました。
お盆のご供養もまた、ご先祖様への利他行であると言えましょう。ご先祖様が安らかであることを願い、心を込めてご供養するその行いは、巡り巡って私たち自身の心をも豊かにし、感謝の念を深めてくれます。
また、瑩山禅師は「報恩」ということも大切にされました。ご先祖様が私たちに与えてくださった恩に報いること。それは、ご先祖様の「いのち」を受け継いだ私たちが、今を精一杯生き、そして未来へと「いのち」を繋いでいくことでもございます。
今を生きる私たちにできること
私たちはお盆のご縁に際し、ご先祖様から頂いた「いのち」を今、ここで確かに生かしていることに感謝し、その「いのち」を大切にすること。そして、その「いのち」を未来へと繋いでいくこと。これこそが、ご先祖様への何よりのご供養になるのではないでしょうか。
ご先祖様は、私たちが幸せに生きることを、きっと願っていらっしゃいます。日々の生活の中で、感謝の心を忘れず、誰かのために尽くす「利他」の心を育むこと。そして、坐禅を通して自分自身と向き合い、心の安らぎを見出すこと。これらの実践こそが、お釈迦様、道元禅師、瑩山禅師の教えにかなう、このお盆というご縁に相応しい生き方であります。
お盆のご供養を通して、私たちはご先祖様との縁を再確認し、自身の「いのち」の尊さを改めて感じることができます。そして、この尊い「いのち」を、より良きものとして次代へと繋いでいくことこそが、私たちの使命です。
皆様のご先祖様のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、皆様のこれからの日々が、感謝と安らぎに満ちたものとなりますよう、心より念じております。
合掌